毎日使っている布団だけど、洗ったほうがいいのかな?
と悩んでいませんか?
いくらシーツやカバーを変えていても、汗は染み込むしカビや臭いも気になりますよね。
布団は、衛生面を考えると1年に1~2回洗濯するのが望ましいです。
しかし、頻繁に洗濯すると布団を傷めてしまうため2~3年に1回の頻度での洗濯がおすすめです。
洗っていない布団では、カビやダニ、臭いなどでアトピーや喘息など体にもよくありません。
もちろん、体に症状が現れなくても寝心地が悪くなり、睡眠の質も落ちてしまうでしょう。
この記事を読むことで、あなたのこんな悩みを解決します。
- 布団は洗濯したほうがいいの?
- 日頃のお手入れの仕方が知りたい
- 布団を洗濯するタイミングはいつ?
- 布団を洗濯するときの注意点は?
- クリーニング業者を選ぶコツは?
布団のメンテナンスをきちんとすることで、気持ちの良い睡眠をとることができ疲れもしっかりとることができますよ。
布団を洗濯するべき理由と必要性

布団を定期的に洗濯することで、睡眠環境が良くなり、質の良い睡眠をとることができます。
特にダニやハウスダストによるアトピーや喘息などの睡眠を妨げる原因を除去することができます。
しかし、そう頻繁に布団を洗うことはできないため、日頃のお手入れが必要です。
ダニやハウスダストには、寝具を清潔な状態に保つことが大切になります。
布団も定期的に干す他、除湿シートを活用したり、寝室の湿気対策も忘れずに行います。
布団を敷きっぱなしの状態である万年床も、カビの原因になるのでやめましょうね。
ダニやハウスダストの除去は重要!!
布団に潜んでいるダニやハウスダストにより、体調を崩してしまうことがあります。
特にダニの死骸や糞、脱皮殻は特に強いアレルゲンとなるのです。
これにより、喘息、鼻炎、アトピー性皮膚炎、結膜炎などの発症や悪化のリスクが高まるため、早めの除去が必要になります。
しかも、ダニが好む高温多湿な環境が整いやすいため、対策が必要になります。
定期的に布団クリーナーで、ダニやハウスダストを吸い取るようにしておきましょう。
汗・皮脂・汚れの蓄積を防ごう
布団は、汗や皮脂、汚れが蓄積しやすい場所です。
こういった汚れを防ぐためには、以下の5つの対策が効果的です。
- シーツや敷きパッドを定期的に洗濯
- 布団を天日干しや風通しの良い場所で干す
- 布団乾燥機や除湿シートの活用
- 寝室の換気と湿気対策を行う
- 洗えるものは適切な洗濯方法で洗う
普段は、なかなか洗うことができないため、干したり部屋の湿気を取り除いたりなど湿気対策が重要となります。
ちょっと大変ですが、シーツや敷きパッドなど、洗濯機に入るものはこまめに洗いましょう。
洗うことにより、ダニの餌を減らすことができ、気持ちの良い布団で眠ることができますよ。
シーツや敷きパッドを定期的に洗濯
汗や皮脂による汚れや黄ばみを防ぐためには、シーツや敷きパッドをこまめに洗濯しましょう。
特に顔や首に触れる枕カバーは毎日か2日に1回の洗濯が理想です。
布団を天日干しや風通しの良い場所で干す
布団は週に1回程度、晴れた日に天日干しをして湿気を飛ばしましょう。
木綿やポリエステルは片面30〜40分ずつの天日干し、羊毛やウレタン素材は風通しの良い場所で干すだけでも効果的です。
布団乾燥機や除湿シートの活用
布団乾燥機で高温乾燥を行ったり、敷き布団の下に除湿シートを敷くことで湿気を取ることができます。
湿気を取ることで、ダニやカビの発生をおさえられます。
寝室の換気と湿気対策を行う
湿気をためないためにも寝室の風通しを良くすることも重要です。
また、カビやダニの繁殖を促すことになるため、換気をして湿気を追い出しましょう。
洗えるものは適切な洗濯方法で洗う
タオルケットや敷きパッドなどは、洗濯ネットに入れて定期的に洗いましょう。
洗濯ネットに入れて洗うことで、洗濯時の摩擦が減り、毛玉や型崩れなどが防止できます。
また、汚れがひどい部分は前処理をすると汚れ落ちが良くなります。
臭いやカビの予防で衛生的にしよう
布団は、人の汗や皮脂、湿気を吸収しやすいため、カビや臭いが発生します。
カビが発生するとアレルギーや健康被害のリスクも高まるため、早めの対策が必要です。
カビや臭いの予防と衛生管理のポイントは、5つあります。
- こまめに布団を干す
- 布団乾燥機や除湿剤の活用しよう
- 収納時にも工夫をしよう
- 万年床はやめよう
- プロのクリーニング活用しよう
布団に生えたカビは、一度生えると家庭できれいに取ることは不可能です。
布団をしっかりと乾燥させることや、敷きっぱなしにしない、仕舞う場所にも湿気をためない工夫をしましょう。
それでもカビが生えてしまった場合は、早めにクリーニング業者に相談することで、きれいにカビを落とすことができますよ。
こまめに布団を干す
布団は、週に1回を目安に3~5時間、天日干しや風通しの良い場所で干しましょう。
こうすることで、内部の湿気を除去しカビの発生を防ぎます。
布団乾燥機や除湿剤の活用しよう
天日干しが難しい場合は、布団乾燥機を使って乾燥させます。
押し入れにしまうときには、除湿剤や炭八等の調湿剤を押入れや布団の下に設置することで湿気対策ができます。
収納時にも工夫をしよう
収納する前には、必ず布団を十分に乾燥させてから収納しましょう。
また、直接布団を押し入れに入れず、通気性の良いすのこを置いたり、除湿マットを使ったりして湿気がこもらないようにします。
万年床はやめよう
布団を敷きっぱなしにすると湿気がこもり、布団だけではなく床にまでカビが生えてしまうことがあります。
布団は敷きっぱなしにはせず、毎朝上げて湿気を逃がしましょう。
プロのクリーニング活用しよう
家庭では丸洗いできない布団や、カビがひどい場合は、専門のクリーニング業者に依頼しましょう。
クリーニングをすることで、カビや汚れを取り除き、衛生状態を保つことができます。
アレルギーや喘息対策として布団の洗濯は必要
アレルギーや喘息の主な原因として、寝具の不衛生さが挙げられます。
布団やシーツにはダニやハウスダスト、花粉、汗や皮脂などのアレルゲンが蓄積しやすくなっています。
このアレルゲンの蓄積が、喘息やアレルギー症状の悪化につながります。
特に寝具は、寝ている長時間肌に触れるため、アレルゲンの影響を直接受けやすいです。
つまり、定期的な洗濯が、喘息やアレルギー症状の予防・軽減に非常に効果的です。
シーツやカバーは週1回程度、汗をかきやすい時期や症状が重い場合はさらに頻度を上げましょう。
布団自体も丸洗いできるものは半年から1年に1回、もしくは症状に応じてもっと頻繁に洗うことで、症状が緩和できます。
布団の洗濯頻度の目安と基準は種類によって違う!!

布団の洗濯頻度は、基本的には年に1〜2回と言われています。
しかし、季節や環境によって洗濯の頻度を変えることも必要です。
汗をかきやすい夏は、頻度を増やしたり、乾燥する冬は頻度を減らしたりすることで、衛生的になります。
羽毛布団は、綿や羊毛の布団に比べ湿気を吸いにくいため、洗濯頻度を減らしても大丈夫と言えます。
しかし、汗や皮脂などの汚れはつくため、羽毛布団は秋冬用にしたり、カバーをこまめに洗ったりしましょう。
一般的な布団の洗濯頻度は年に1〜2回
一般的な布団の洗濯頻度としては、衛生面を考慮すると「年に1~2回」が適切です。
具体的には、春と秋の季節の変わり目に洗うのが理想的と言えます。
また、同じ布団を1年中使い続ける場合は、半年に1回程度の洗濯が推奨されることが多いです。
季節や気候によって洗濯頻度は調整しよう
布団は、年に1〜2回洗うのが適切ですが、季節や気候に合わせて洗う頻度を調節するのもおすすめです。
布団を洗濯するタイミングは、以下のとおりです。
| 季節 | タイミング |
|---|---|
| 春・秋 | 夏布団から冬布団に入れ替えるタイミングで洗濯 |
| 夏 | 必要に応じて洗濯頻度を増やす 汗を多くかいた場合は早めに洗う |
| 冬 | 洗濯頻度は控えめでOK ただし汚れや臭いが気になる場合は洗う |
また、高温多湿な地域や梅雨時期は、ダニやカビの発生リスクが高まります。
洗濯や布団干し、乾燥機の活用を積極的に行いましょう。
布団の種類によって洗濯頻度は変わる!!
普段の丸洗いは、布団の種類によって洗濯頻度は変わります。
特に水に弱い羽毛布団は、頻繁に洗いすぎるとかさや保温性を損なうので、注意しましょう。
布団の種類別の洗濯とクリーニング頻度の目安は、以下のとおりです。
| 布団の種類 | 洗濯の頻度 | 洗濯の方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 羽毛布団 | 5~7年に1回 | クリーニング | 頻繁な洗濯は羽毛や側生地を傷めるためるのでNG カバーのこまめな洗濯と天日干しで日常ケアをしよう |
| 綿布団 | 1~2年に1回 | クリーニング | 汗や皮脂を吸収しやすいので、羽毛布団よりも高めの頻度がおすすめ 自宅での洗濯は難しいため専門クリーニングが安心 |
| 羊毛布団 | 1~2年に1回 | クリーニング | 吸湿性が高く、湿気を含みやすい 自宅で洗えるものもあるが、必ず洗濯表示を確認してから洗うこと |
適切な洗濯頻度と日頃のお手入れで、布団を長持ちさせることができるので、覚えておきましょう。
布団の洗濯のタイミングとサインを見極めよう

布団を洗濯するのは一大イベントなので、タイミングやサインを見極めて洗うことをおすすめします。
まず、布団を洗濯するときの判断ポイントしては、臭いや湿気、ダニの前兆です。
臭いがしてきたり、ダニによるかゆみなどがで始めてきたら、洗濯をするタイミングだと思いましょう。
また、季節の変わり目である春や秋に使っていた布団を洗濯するのもおすすめです。
シーズン終わりに洗濯することで、きれいな状態で保管できます。
さらに、布団が完全に乾くまで時間がかかったり、クリーニング業者が混んでいたりしても、時間の余裕ができるので安心ですよ。
布団の洗濯の必要性を判断するポイントは3つ
布団を洗濯するかどうか見極めるポイントは3つあります。
- 臭い
- 湿気
- ダニの前兆
布団に汗や皮脂、アカ、フケなどが染み込むと、雑菌が繁殖して嫌な臭いが発生します。
布団を嗅いでみて、嫌な臭いがし始めたら洗濯やクリーニングを検討するポイントです。
また、人は寝ている間にコップ1杯以上の汗をかくため、布団の内部は湿気が溜まりやすい状態です。
カビやダニの繁殖に適した環境となるため、布団の天日干しや陰干しで湿気を取り除いたり、必要に応じて洗濯をしましょう。
もしも、寝ている時にかゆみやアレルギー症状が出たら、ダニの可能性があります。
ダニに噛まれなくても死骸や糞もアレルギーの原因となるため、掃除機などで吸い取るのもおすすめです。
季節の変わり目や気候条件に合わせた洗濯タイミング
季節の変わり目や気候条件に合わせて布団を洗濯するのもおすすめです。
布団を洗濯するのに最適なタイミングは、春と秋です。
もっと詳しく説明すると春は5月頃、秋は10月から11月頃が洗濯に最適なタイミングと言えます。
春は冬布団を片付ける前に、秋は夏布団を片付ける前に洗うことで、1年の間に蓄積した汚れやダニ、アレルゲンをしっかり除去できます。
日常的には、カバーをこまめに洗い、天日干しで湿気を飛ばしましょう。
また、洗濯は天気が良く、気温が高い日を選び、布団の中までしっかり乾燥させることが重要です。
乾燥不足は、カビやダニの原因となるので、注意しましょう。
布団を洗濯前に確認すべきポイントは4つ!

布団を洗濯するときは、注意しなければいけないことは4つあります。
- 布団の素材と洗濯表示の確認
- 洗濯中に気をつけるべきポイント
- 洗濯後の乾燥とカビ・ダニ対策
- 洗濯後に起こりやすいトラブル
布団は、素材によって特徴や洗濯方法が違います。
綿や羊毛、絹は基本的には洗濯不可です。
また、洗濯前には洗濯表示や洗い方を確認しておきましょう。
洗濯後は、しっかり乾かすことで、カビの防止になります。
布団を丸めて中綿がよらないようにしたり、干した後に形を整えたりなど、ひと手間加えることでトラブル防止になります。
ちょっとめんどくさいですが、洗濯の失敗を防ぐためにもしっかり対策をしましょうね。
布団の素材と洗濯表示の確認方法
布団を洗濯する前に、普段の素材を確認しておきましょう。
もし、布団の買い替えを検討しているのであれば、質感やお手入れのしやすさも大切です。
まずは、以下の表からあなたにあった布団を見つけてくださいね。
| 素材 | 特徴 | 洗濯の可否 |
| 綿(コットン) | 天然繊維で、夏は涼しく冬は暖かい。 吸湿性・保温性・弾力性に優れ、肌ざわりがよい。 日干しでふっくらと蘇る。 | 洗濯不可 洗うと繊維が絡まりダマになり、寝心地が悪くなるため、家庭での洗濯は不可。 |
| 合成繊維(ポリエステルなど) | 軽くて弾力性があり、保温性も高い。 吸湿性はやや低いが、透湿性があり蒸れにくい。 洗えるタイプや防ダニ・防臭・抗菌加工など、機能性に優れた製品が多い。 | 洗濯可 家庭用洗濯機で丸洗いできるものが多く、最も扱いやすい素材。 軽量で乾きやすく、アレルギー対策にも適している。 |
| 羊毛(ウール) | 保温性・吸湿性・放湿性に優れ、冬に特に人気。 弾力性があり、型崩れしにくい。 | 洗濯不可 洗濯するとフェルト化し、硬くなったり縮んだりする。 家庭洗濯は避け、クリーニング店に相談するのが安全。 |
| 羽毛(ダウン) | 非常に軽く、保温性が抜群。 吸湿・放湿性にも優れている。 | 一部洗濯可 洗濯表示で「水洗い可」となっているものは洗濯可能。 キルティング加工が施されていることが多く、中身の偏りを防ぐため洗濯しやすい。 |
| 絹(真綿) | 軽くて柔らかく、保温性・吸湿性・放湿性に優れる。 静電気が起こりにくく、肌にやさしいが、デリケートで家庭洗濯は難しい。 | 洗濯不可 デリケートな素材のため、家庭での洗濯は不向き。 |
ここでは、合成繊維や一部の羽毛布団が洗えると紹介しましたが、洗う前にしっかりと洗濯タグをチェックしておきましょう。
以下のタグが洗えるか洗えないかがわかるタグの一部の表記です。

タグを調べて洗えるなら洗濯、洗えないならクリーニング業者に依頼しましょう。
洗濯中に気をつけるべきポイント4つ
布団を洗濯するときに気をつけるべきポイントは4つあります。
洗濯前
水洗い可能かどうか。
洗濯不可のマークがあったらクリーニングに出す。
キルティング加工がされていない場合は、中綿が偏りやすいので、丸めた後に紐で数か所縛ってから洗うとよれ防止になります。
洗濯機に布団が洗えるほどの容量があるかどうか。
ドラム式洗濯機は、布団洗いに向かない場合があるので注意が必要です。
洗剤と洗濯方法
使う洗剤は、中性洗剤(おしゃれ着用・衣類用)を選ぶこと。
アルカリ性洗剤や一般的な洗濯洗剤は羽毛や中綿を傷める原因。
洗剤は水にしっかり溶かしてから投入する。
布団に直接かけない。
布団を洗うときは、必ずネットを使用し、布団は縦に三つ折り後、くるくる巻いて空気を抜いてネットに入れる。
洗濯コースは「布団・毛布コース」や「大物洗いコース」、ない場合は「手洗いコース」など優しいコースを選ぶ。
水温と洗濯機の使い方
高温は羽毛や中綿の劣化を招く。
洗濯機に布団を入れた後、数分間浸け置き洗いをすると汚れ落ちが良くなる。
乾燥・干し方
中まで乾かないとカビや臭いの原因になるため、2~3日かけて干す。
物干し竿2本にまたがせてM字型に干すと、重みで素材が偏るのを防ぎ、乾きも速くなる。
時々叩いて固まった羽毛をほぐすとふんわり仕上がる。
直射日光による色あせが気になる場合は、布団の上からカバーをかけて陰干しする。
乾燥機を使う場合は低温設定で、大型乾燥機を使う。
普段はなかなか買い替えや捨てるのも大変なので、洗濯を失敗すると悲惨なことになるのできちんと上記の点を守りましょう。
洗濯後の乾燥とカビ・ダニ対策
洗濯後はしっかり乾かすことが、カビやダニ対策のポイントになります。
布団を洗濯した後の乾燥でおすすめなのが、乾燥機の活用です。
特にコインランドリーの乾燥機は、大きな布団もしっかり乾かせます。
高温設定にすることで、ダニも死滅させる効果があります。
また、タンブラー式の乾燥機にテニスボールを1〜2個入れると、布団が叩かれてふっくら仕上がり、乾燥ムラも防げます。
回転しながら乾燥させる乾燥機です。
乾燥後は、布団を広げて空気を含ませるように形を整えると、さらにふわふわになりますよ。
洗濯後に起こりやすいトラブルとその対処法
自分で布団を洗濯すると以下のようなトラブルが起きることがあります。
- ぺちゃんこになる(ふんわり感の喪失)
- 中綿・羽毛の片寄り
- 生地の破れ・穴あき
- 洗濯前より臭くなる・カビ臭が残る
自分でも対処できますが、100%対処できるわけではないので、不安な場合はクリーニング業者に依頼しましょう。
ぺちゃんこになる(ふんわり感の喪失)
羽毛布団では、洗剤や柔軟剤の選択ミスや水洗い不可の布団を洗濯した場合にぺちゃんこになってしまうことがあります。
これは、羽毛のコーティングが取れてしまうからです。
羽毛布団は、乾燥機を使って十分に乾燥させることにより、羽毛や中綿がふっくら戻る場合があります。
また、羽毛をふんわりさせるために、乾燥機にテニスボールなどを一緒に入れると効果的です。
中綿・羽毛の片寄り
洗濯や脱水時に強い力が加わったり、適切なコースを選ばなかったりで、中綿や羽毛が一箇所に固まってしまうことがあります。
片寄った状態では、寝心地はもちろん、保温性にも欠けてしまいます。
乾燥後は、布団を軽く叩いたり、手で揉みほぐして中身を均等に戻す作業を繰り返しましょう。
また、完全に元に戻らない場合もあるため、洗うときは「大物洗いコース」や「毛布コース」を選び、洗濯ネットを使用しましょう。
側生地の破れ・穴あき
洗濯ネットを使わなかったり、洗濯機の通常モードで洗ったりすると、生地が破れて中身が出てしまうことがあります。
手縫いで補修できるほどの小さな破れは、手縫いで縫い合わせましょう。
しかし、大きな破れや中身が大量に出てしまった場合は、専門のクリーニング店やリフォームサービスに相談するようにすると安心です。
洗濯前より臭くなる・カビ臭が残る
十分に乾燥できていないと、湿気が残りカビや臭いの原因になります。
乾燥機や布団乾燥機、サーキュレーター、扇風機を使い、芯までしっかり乾燥させましょう。
湿気が残ると再度カビや臭いが発生するため、念入りに乾燥させることが重要となります。
ついてしまった臭いには、衣類スチーマーで臭いを取ってから乾燥させると臭いを消せますよ。
衣類スチーマーの高温の蒸気が、臭いのもとを除去してくれるのです。
詳しくは、こちらの記事で紹介しています。
【女子必見】一人暮らしには衣類スチーマーが良い理由3つ!アイロンとの違いも紹介
布団の長持ちさせるためのメンテナンス方法

布団を長持ちさせたいのであれば、メンテナンスが必要です。
定期的に天日干しをするのにも、干す時間帯や干し方で布団の耐久性は変わります。
長時間干したり、布団たたきでたたいたりすると布団を痛める原因になるので避けましょう。
また、布団を押し入れにしまうときは、湿気がたまらないように毎日扉を開けることが必須です。
布団の耐久性を保つためには、クリーニングは2~3年に1回の頻度に抑えます。
クリーニング業者も完ぺきではないため、布団の専門知識があることや口コミを参考にしてから依頼しましょうね。
定期的な天日干しの効果
布団を定期的に天日干しすると、湿気を取り除いたり、カビやダニの繁殖を一時的に抑えることができます。
これは、日光の紫外線による殺菌作用を利用し、雑菌の繁殖を防ぎ、汗や皮脂による嫌な臭いを軽減できるからです。
さらに、布団がふっくらと軽くなるので、寝心地や睡眠の質が向上します。
ポイントは5つ。
- 晴れて湿度が低い10時〜15時頃に干す
- 1回の天日干しは夏1〜2時間、冬は半日
- 普段の裏表をそれぞれ干す
- 布団叩きで叩くのはNG
- 布団カバーやシーツをかけたまま干すと日焼け防止になる
晴れた日の湿度が低い時間帯を狙って干すと、普段の湿気を取ることができます。
しかし、長時間干すと日焼けなど生地が傷みやすくなるため、カバーやシーツをかけたまま干しましょう。
また、裏表をそれぞれ干すことで、しっかりと湿気をとることができます。
布団を干す時についつい布団叩きで布団を叩きがちですが、中綿がきれてしまうので、掃除機でホコリなどは取りましょう。
布団を長持ちさせるためにも、上記の点を守って干してくださいね。
収納時の注意点と防虫対策
布団を収納するときは、しっかりと乾燥させてから仕舞わないと、カビ臭やダニの繁殖の原因になります。
また、収納場所である押し入れやクローゼットは、湿気がこもりやすいため、毎日扉を開けて換気しましょう。
すのこやラックを使い床から浮かせることやぎゅうぎゅうに詰め込まないなど、空気の通り道を作りましょう。
防虫・防ダニ加工の収納袋なら、同時に虫の侵入やダニの反応を防ぐことができますよ。
収納袋を使わずに仕舞うのであれば、 布団用防虫剤(パラジクロルベンゼン製剤など)や、防ダニシート・置き型シートを押入れに入れておくと効果的です。
また、布団やカバーに付着したホコリや皮脂は、虫やダニの栄養源になるため、収納前に掃除機をかけ、カバー類も必ず洗濯してから保管しましょうね。
収納に自信がない場合は、クリーニング業者で次のシーズンまで預かるサービスがあるので、利用するのも手ですよ。
クリーニングに出すタイミングと選び方
布団をクリーニングに出すときは、以下のタイミングで出すことをおすすめします。
- 季節の変わり目
- 使用後のシーズン終わり
- 2~3年に1回の頻度
クリーニングも洗濯と同じように季節の変わり目に使用していた布団を出しましょう。
汗や皮脂がつ布団にたまった状態では、カビや雑菌が増えるため、使い終わった直後にクリーニングに出すのがおすすめです。
しかし、毎回クリーニングに出すと布団の耐久性の面からすると、綿や絹でも2~3年に一回の頻度に抑えておいたほうが良いでしょう。
また、クリーニング業者に出すときには、布団に対応できる業者であるかや保証の有無、口コミなどの評判もチェックしておくと安心です。
布団を持たないのも1つの手!サブスクでメンテナンスいらず

最近では、布団もサブスクで借りることができます。
- 収納スペースが必要ない
- 季節に合わせた布団が使える
- シーツのセッティング不要
- 高級布団で睡眠の質UP
- 捨てる手間がない
本来、布団も季節に合わせて使うものですが、収納スペースがなかったり、高級な羽毛布団などは高くて2つも買えなかったりします。
また、古くなったり引っ越したりなど、布団を処分したいのにどのように捨てたらよいかわからない人もいますよね。
そんなときも、サブスクなら季節に合わせて布団を交換、処分する必要もありません。
特にRAKUTONは、羽毛布団が月々3,278円~使うことができます。
年間39,336円!!
ちょっと良い羽毛布団1つの金額で、季節に合わせた布団が使えます。
メンテナンスの手間もないので、忙しいあなたにぴったりですよ。
まとめ
- 布団は汗や皮脂汚れ、ダニの繁殖など衛生面を考えたら1年に1~2回の洗濯がおすすめだが、布団が傷みやすくなるため2~3年に1回、羽毛布団は5~7年に1回の洗濯がおすすめ
- 布団を長持ちさせる日頃のお手入れとして、定期的に布団を干し、最低でも1週間に1回はシーツやカバーを洗うこと
- 布団を洗濯するタイミングは、季節の変わり目である春や秋の他、臭いやダニの前兆など汚れが気になったタイミングで行う
- 布団を洗濯するときは、洗濯表示で洗えることを確認し、洗濯後はしっかりと時間をかけて乾かすこと
- クリーニング業者を選ぶときには、布団の専門知識や口コミなどを調べてから選ぶと良い
布団を洗濯するのはとても大変です。
しかも、思ったようなふんわり感を得られない場合もあり、私としてはクリーニングやサブスクでプロによるメンテナンスが気持ちの良い布団にする方法だといえます。
あなたもこれを機会に、布団についてもう一度考えてみませんか?
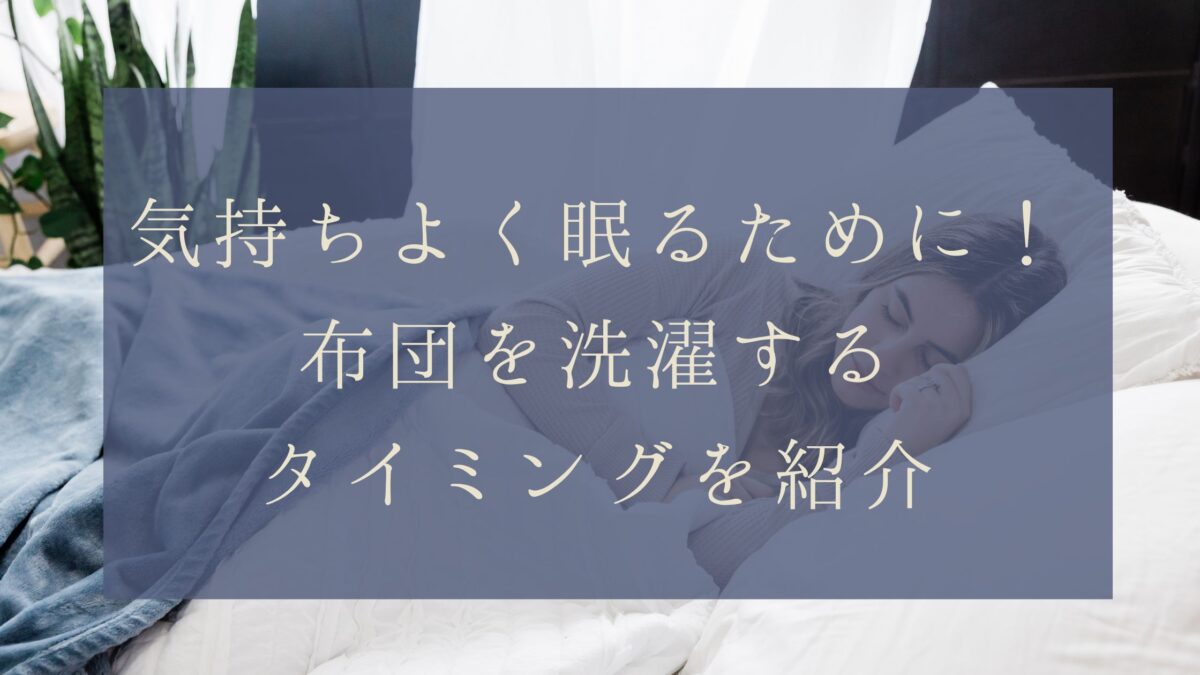
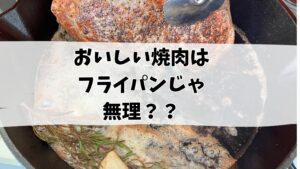

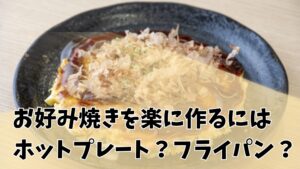
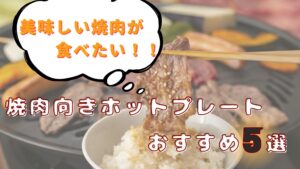




コメント